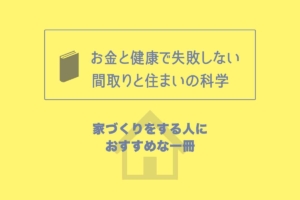どうも、しんば(@shimbakone)です。
我が家を建てた工務店の換気システムは、標準仕様でパイプファン(のダクトレス第3種換気)でした。換気について考えた結果、我が家ではパイプファンをやめる判断をしました。
コロナウイルスの事もあって、これから家づくりをする方は換気についても気にされる方が増えるのではないかと思います。そこで今回はパイプファンをやめた理由を整理してみました。
それはいってみましょう!
パイプファンとは
我が家は地方の工務店で建てたのですが、換気システムは標準設定としてパイプファンを使った換気(ダクトレスの第3種換気)でした。

出典:Panasonic
プロペラが回転し、軸の向きに空気を押し出して排気する、シンプルなファン。他のファンに比べると空気を押し出す力(静圧)が弱い。
このようなパイプファンがトイレなどについており24時間運転する事で排気をします。一方、居室の壁などには給気口が設置され、ここから外気が取り込まれます。パワーが弱いため、1階、2階それぞれで給気口、排気口を設置するような形になります。
パイプファンは第3種換気という区分に属しており、
排気 : 強制的に排気(機械排気)
吸気 : 自然に吸気
という換気方法です。排気しようとする力によって負圧(室外よりも室内側の気圧が低い状態)を作ります。空気は気圧の高い所から低い所に流れるため、室外から空気が取り込まれるという仕組みを利用して換気を行います。
ローコストに設置できるものなので、価格面ではメリットがあるのですが、換気能力としてはあまり優秀ではないのです。
パイプファンをやめた理由
では、結論を書いてしまうと、
標準仕様(パイプファン)では十分な換気がされるのか疑問だった
という事です。理由としては、
- パイプファンはパワー(静圧)が弱いため
- 建物の気密が高いため(目標C値は0.3)
- ファンを複数つけても単純に足し算で換気がされるわけではないため
というところです。
換気が適正に機能しない場合、人の健康だけではなく、建物の健康も悪化させてしまうという問題が発生します。よって、換気システムを検討し、しっかり換気の機能を発揮させたいと考えました。
換気の重要性はこちらの記事で解説しています。

では、パイプファンをやめた理由を詳しく解説しますね。
パイプファンの換気量低下問題

私が問題視した根拠はこちらのサイトで指摘されていた内容です。
実際にパイプファンの換気量を測定した人の話によると、窓を閉め切った状態での測定値は窓を開けた状態、つまり負圧が発生しない状態での測定値の半分しかでなかったというのです。ちなみにそのパイプファンはごく普通のもので、窓を閉めた状態での換気量は15立方メートル/hだったそうです。これには測定者もビルダーも驚いてしまったといいます。
該当記事の内容を要約すると、(第3種換気のパイプファンにおける話)
- カタログ値通り換気能力が発揮されない
- 「外から強風が吹く時」や「建物の気密が高い時」は空回りして換気量が低下する
- 静圧が低いファンは、換気量がカタログ値の半分程度になってしまう事を踏まえよう
という事が指摘されています。
パイプファンで換気をする場合において、気密の低い建物であれば(漏気によって自然に換気されるので)そこまで問題はないのですが、C値1.0レベルの気密性になると、パイプファンの力が気密性に負けてしまいます。
つまり「室内の空気を引っ張り出す力が出ない」という事です。
我が家の場合はC値0.3の高気密を目指していたので、こういった理由からパイプファンでは空回りする可能性が高いと判断しました。
これが理由1と2の根拠になります。
ファンを増やせばいいのでは…?
ファンのパワーが弱いのであれば、「ファンの数を増やせば気密に負けないようになるのでは?」と考えた方もいるでしょう。
しかし、空気はそう簡単には動いてくれないのです。
根拠はこちらのブログです。
風量は複数台の和になりますが、静圧はそうはならず、最悪の場合は静圧の低い側のファンから逆流が発生する可能性もある。互いに逆の力を相手に掛けている事になるからである。それでも風量さえ複数台の和になれば良いではないかと思われるかもしれませんが、静圧が低ければ結局風量もその和にならないという事になる。
(中略)
高気密住宅に換気機能付きのレンジフードファンや浴室換気扇を付けても静圧が低い事と互いに干渉しあうことで期待通りの換気量は得られない事。
とまとめられています。
しっかり換気がされるようにファンの数を増やしたとしても、単純に換気量が2倍3倍となるわけではなく、むしろ互いに引っ張り合い換気能力が低下する場合も…という事ですね。
これが理由3の根拠です。
(流体力学を学べばもう少し詳しいイメージがつかめるかもしれません)
対応策

ということで、第3種換気においては、
複数のファンを設置するよりも、大きなパワー(静圧)のあるファンを1つだけ設置する方が、干渉問題を抑えられる
と考えられます。
大きなパワーのあるファンとは
- シロッコファン
- ターボファン
と呼ばれるもので、こういったファンを使えば上記のような問題は起きないでしょう。詳しい説明は省きますが、これらは風を送り出す羽の形状がパイプファンと大きく異なり、パワー(静圧)を出すことができるのです。
ダクトレスの第3種換気であれば、日本スティーベル社のLA60がおすすめです。静圧がかなり高いので、気密に負けるようなことにはならないでしょう。しっかり換気計画を検討しているブロガーさんの住宅ではこれが採用されている印象です。
ダクト式第3種換気はファン1台で集中排気を行うので、必ずパワーのあるファンになっているはずです。よってこのような心配は不要でしょう。日本住環境株式会社のルフロ400とかですね。
大手ハウスメーカーではパイプファンを使っていないと思うので大丈夫かと思いますが、気をつけるのはローコストメーカーで建てる場合かなと思います。仕様を確認してくださいね。
おわり
パイプファンの問題点を整理しました。私がパイプファンをやめた理由は、
- パイプファンはパワー(静圧)が弱いため
- 建物の気密が高いため(目標C値は0.3)
- ファンを複数つけても単純に足し算で換気がされるわけではないため
ということでした。
これからの住宅は気密性がそこそこ高まってきている(と思っている)ので、換気システムとしてのパイプファンでは役不足感が否めません。
また、インフルエンザ・コロナウイルス等の対策として換気が求められますので、窓を開けず24時間換気でしっかり換気ができるように設計されている必要があると思います。
いずれにしても、パイプファンだけ避けたほうが良いでしょう。
最後まで読んでいただいてありがとうございました。